おいしいもの
閲覧ありがとうございます! ジャンルに関係なく、いろいろな記事を綴っていこうと思います。※2012/1/3開設
2012.01.14
こんにちは。
今日はセンター試験の日ですね。
私も数年前に受けましたが、懐かしい思い出です。
*
さて、今回はよく家庭で使う代表的な調味料
「しょうゆ」
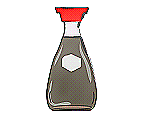
についてまとめてみます。
まずは、しょうゆの分類について。
しょうゆを分類するには、いろいろな方法があります。
日本農林規格(JAS)では
「種類による分類」
「製法による分類」
「等級による分類」 と大きく3つに分けています。
今回は、一番馴染みのある、「種類による分類」について取り上げてみます。
しょうゆは、「こいくち」「うすくち」「たまり」「さいしこみ」「しろ」の5つの種類に分類されます。
●こいくちしょうゆ(濃口しょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の8割以上を占めるしょうゆ。
・食塩分は約16%
・調理用、卓上用のどちらにも幅広く使える万能調味料。
●うすくちしょうゆ(淡口しょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の1割程度を占める。
・食塩分は18~19%
(製発酵・熟成が進んで色が濃くならないように高濃度の食塩を加えている。醸造過程の仕上げとして、甘酒や水あめを加える特徴もある、)
・炊きあわせやふくめ煮など、素材の色や風味を生かして仕上げる調理に使われる。
●たまりしょうゆ(溜しょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の2%弱ほど。
・食塩分は約16%
・原料はほとんど大豆だけ
・寿司や刺身などの卓上用、照り焼きなどの調理用や、佃煮、せんべいなどの加工用にも使われる。
●さいしこみしょうゆ(最仕込みしょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の約1%。
・食塩分は約16%
・しょうゆを2度醸造するような製法であることからこの名前がついた。
・色、味、香りともに濃厚で、別名「甘露しょうゆ」や「刺身しょうゆ」とも言われる。
・刺身、寿司、冷奴など、主に卓上用で用いられる。
●しろしょうゆ(白)
・日本のしょうゆ生産量の1%弱。
・食塩分は約18%
・糖分が12~16%で比較的高い。
・色の薄さと香りを生かした吸い物や、茶碗蒸しなどの料理、せんべい、漬物などにも使用される。
この5つの種類の中で一番日本で生産量の多いのは「こいくち」であることから、
私たちが”しょうゆ”と聞いて最初にイメージするものも、殆どが濃口しょうゆであると思います。
「うすくち」と「こいくち」。これは上で述べたように、うすくちはこいくちより塩分濃度が高く作られています。
見た目で薄い色をしているからと言ってたくさん料理に使いすぎないように注意しなければいけませんね。
また、しょうゆにもいろいろあって、大豆を原料としていないしょうゆも存在します。
例えば、私の今いる石川では、ぎょしょう(魚醤)(またはいしる、いしりなどとも呼ばれている)ものがあります。これは、イワシやイカなどの魚類を原料に発酵させ、しょうゆとして製造するものです。最近生活習慣病で気になる塩分も減塩醤油と同じくらいだということで、体にもよいとされています。
石川にお越しの際には、是非魚醤を手土産にいかがでしょうか
次回しょうゆについての記事を書くときにはしょうゆの効果・効能についてまとめてみたいと思います。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

にほんブログ村
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
今日はセンター試験の日ですね。
私も数年前に受けましたが、懐かしい思い出です。
*
さて、今回はよく家庭で使う代表的な調味料
「しょうゆ」
についてまとめてみます。
まずは、しょうゆの分類について。
しょうゆを分類するには、いろいろな方法があります。
日本農林規格(JAS)では
「種類による分類」
「製法による分類」
「等級による分類」 と大きく3つに分けています。
今回は、一番馴染みのある、「種類による分類」について取り上げてみます。
しょうゆは、「こいくち」「うすくち」「たまり」「さいしこみ」「しろ」の5つの種類に分類されます。
●こいくちしょうゆ(濃口しょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の8割以上を占めるしょうゆ。
・食塩分は約16%
・調理用、卓上用のどちらにも幅広く使える万能調味料。
●うすくちしょうゆ(淡口しょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の1割程度を占める。
・食塩分は18~19%
(製発酵・熟成が進んで色が濃くならないように高濃度の食塩を加えている。醸造過程の仕上げとして、甘酒や水あめを加える特徴もある、)
・炊きあわせやふくめ煮など、素材の色や風味を生かして仕上げる調理に使われる。
●たまりしょうゆ(溜しょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の2%弱ほど。
・食塩分は約16%
・原料はほとんど大豆だけ
・寿司や刺身などの卓上用、照り焼きなどの調理用や、佃煮、せんべいなどの加工用にも使われる。
●さいしこみしょうゆ(最仕込みしょうゆ)
・日本のしょうゆ生産量の約1%。
・食塩分は約16%
・しょうゆを2度醸造するような製法であることからこの名前がついた。
・色、味、香りともに濃厚で、別名「甘露しょうゆ」や「刺身しょうゆ」とも言われる。
・刺身、寿司、冷奴など、主に卓上用で用いられる。
●しろしょうゆ(白)
・日本のしょうゆ生産量の1%弱。
・食塩分は約18%
・糖分が12~16%で比較的高い。
・色の薄さと香りを生かした吸い物や、茶碗蒸しなどの料理、せんべい、漬物などにも使用される。
この5つの種類の中で一番日本で生産量の多いのは「こいくち」であることから、
私たちが”しょうゆ”と聞いて最初にイメージするものも、殆どが濃口しょうゆであると思います。
「うすくち」と「こいくち」。これは上で述べたように、うすくちはこいくちより塩分濃度が高く作られています。
見た目で薄い色をしているからと言ってたくさん料理に使いすぎないように注意しなければいけませんね。
また、しょうゆにもいろいろあって、大豆を原料としていないしょうゆも存在します。
例えば、私の今いる石川では、ぎょしょう(魚醤)(またはいしる、いしりなどとも呼ばれている)ものがあります。これは、イワシやイカなどの魚類を原料に発酵させ、しょうゆとして製造するものです。最近生活習慣病で気になる塩分も減塩醤油と同じくらいだということで、体にもよいとされています。
石川にお越しの際には、是非魚醤を手土産にいかがでしょうか

次回しょうゆについての記事を書くときにはしょうゆの効果・効能についてまとめてみたいと思います。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

にほんブログ村
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
PR
2012.01.14
2012.01.13
前回の記事の補足です。
「みょうが」
について、もう少し詳しくまとめてみます。
みょうがはショウガ科ショウガ属の多年草で、日本全国で幅広く栽培され、山地にも自生している。
しかし、これは日本独自であり、外国で野菜として栽培している国はほとんど無いと言われている。
みょうがには主に2種類あって、
「夏みょうが」・・・7月~8月にとれるもの。
「秋みょうが」・・・9月~10月にとれるもの。
みょうがの効能としては、
辛味成分に夏バテや風邪予防の効果がある。
香り成分には、覚醒作用、発汗促進作用、呼吸や血液の循環を良くする、などの効果がある。
※香り成分はアルファピネンと言われ、アルファピネンを含むものの例としてみょうがの他に春菊がある。
また、消化を促進する働きもあるが、生で食べ過ぎると刺激が強すぎて胃に負担がかかる場合があるので注意が必要である。
そこで、生での摂取を控える為に天ぷら、卵とじ、炒め物、汁物など火を通す料理に活用するのがオススメ。
***
みょうがには「物忘れをする」という説もあります。
「みょうが」は漢字で「茗荷」とも書きます。
昔、お釈迦さまに誠実な努力家であるが物覚えが悪く、自分の名前も忘れてしまうため、いつも首に名札をぶら下げていた弟子がいました。
その弟子が亡くなった後に、彼のお墓から見知らぬ草が生えてきました。
生前、彼が自分の名前を 『荷物のようにぶら下げて修行していたこと』 にちなんで、その草を「茗荷」と名づけたということです。
この話から茗荷を食べると物忘れをすると伝えられていますが、医学的、栄養学的な根拠はないようです。
いろいろ書きましたが、みょうがには結構なパワーがあるということが分かります。
料理にも利用価値がある、素敵な食材ですね

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

にほんブログ村
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「みょうが」
について、もう少し詳しくまとめてみます。
みょうがはショウガ科ショウガ属の多年草で、日本全国で幅広く栽培され、山地にも自生している。
しかし、これは日本独自であり、外国で野菜として栽培している国はほとんど無いと言われている。
みょうがには主に2種類あって、
「夏みょうが」・・・7月~8月にとれるもの。
「秋みょうが」・・・9月~10月にとれるもの。
みょうがの効能としては、
辛味成分に夏バテや風邪予防の効果がある。
香り成分には、覚醒作用、発汗促進作用、呼吸や血液の循環を良くする、などの効果がある。
※香り成分はアルファピネンと言われ、アルファピネンを含むものの例としてみょうがの他に春菊がある。
また、消化を促進する働きもあるが、生で食べ過ぎると刺激が強すぎて胃に負担がかかる場合があるので注意が必要である。
そこで、生での摂取を控える為に天ぷら、卵とじ、炒め物、汁物など火を通す料理に活用するのがオススメ。
***
みょうがには「物忘れをする」という説もあります。
「みょうが」は漢字で「茗荷」とも書きます。
昔、お釈迦さまに誠実な努力家であるが物覚えが悪く、自分の名前も忘れてしまうため、いつも首に名札をぶら下げていた弟子がいました。
その弟子が亡くなった後に、彼のお墓から見知らぬ草が生えてきました。
生前、彼が自分の名前を 『荷物のようにぶら下げて修行していたこと』 にちなんで、その草を「茗荷」と名づけたということです。
この話から茗荷を食べると物忘れをすると伝えられていますが、医学的、栄養学的な根拠はないようです。
いろいろ書きましたが、みょうがには結構なパワーがあるということが分かります。
料理にも利用価値がある、素敵な食材ですね

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

にほんブログ村
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
2012.01.13
2012.01.13
こんにちは。
そういえば今日は
「13日の金曜日」
ですね。
13日の金曜日は不吉だと言われていることは皆さんも耳にしたことがあると思います。
では、なぜ不吉と言われているのでしょうか?
それは、↓のサイトによると
「13日の金曜日」恐怖症が広まったのはわずか100年前だった
不吉だと言われているのはただ単に
”何か西洋的な根拠で不吉な日だと思われているが、それは特に根拠があるわけではない。仏滅が悪日だというのと同じくらいの迷信”
とのこと。
その起源はキリスト教がー、などと言われてもいますがどれも根拠は薄いそうです。
今日は13日の金曜日!だからと言って、特に心配する必要はないと思います。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

にほんブログ村
そういえば今日は
「13日の金曜日」
ですね。
13日の金曜日は不吉だと言われていることは皆さんも耳にしたことがあると思います。
では、なぜ不吉と言われているのでしょうか?
それは、↓のサイトによると
「13日の金曜日」恐怖症が広まったのはわずか100年前だった
不吉だと言われているのはただ単に
”何か西洋的な根拠で不吉な日だと思われているが、それは特に根拠があるわけではない。仏滅が悪日だというのと同じくらいの迷信”
とのこと。
その起源はキリスト教がー、などと言われてもいますがどれも根拠は薄いそうです。
今日は13日の金曜日!だからと言って、特に心配する必要はないと思います。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

にほんブログ村



